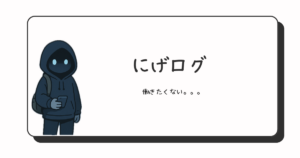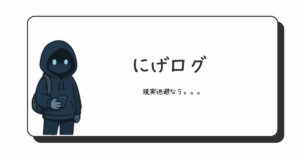働きたくない。でも生きていきたい──今できる現実的な暮らし方
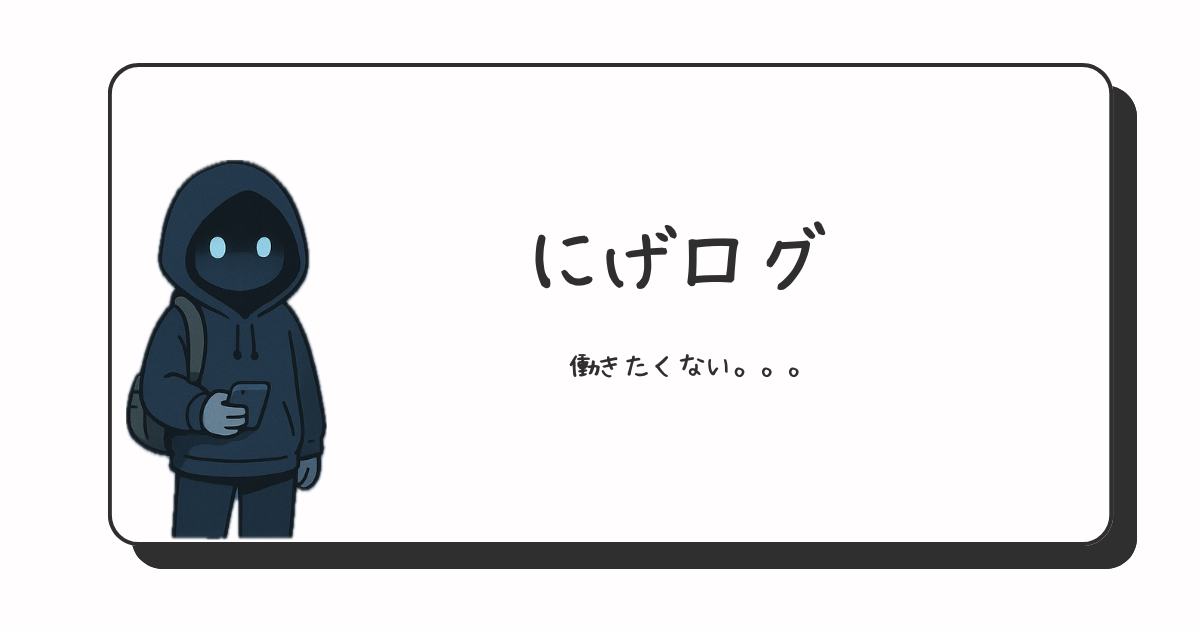
働きたくない。でも生きていきたい──今できる現実的な暮らし方
こんにちは、ニゲルです。
「働きたくない」って言葉、耳にするとドキッとする人もいるかもしれません。
でもボクは、もうその気持ちを否定するのはやめました。
問題は「働きたくないこと」そのものじゃなくて、働かなくても暮らせる方法が、あまりに見えにくいことだと思うんだよね。
「家にいて静かに暮らしたい」
「満員電車も、上司の顔色もうんざり」
「でも家賃払わなきゃ、食費もかかるし…」
そんな葛藤のなかで、現実的にどうやって“逃げながら生きていくか”を、今日は一緒に考えてみようと思う。
「働きたくない」は現実逃避じゃなく、“現実対応”かもしれない
ボクは思うんだ。
昔の働き方って、ずっと我慢して、心も身体もすり減らして、ようやく「正社員」って呼ばれるものでしょ。
でも、いま2025年。もうそういうスタイルに無理して合わせなくていいんじゃないか。
それに、みんな背景が違う。
- 親元に住んでる人
- 地方で家賃2万円のボロアパートに住んでる人
- 東京でひとり暮らししてる人
- 借金がある人
- 貯金が少しある人
「働きたくない」って気持ちの先にある現実も、千差万別なんだ。
まず考えるべきは「いくら必要か?」
ボクがいつも最初にやるのは、「理想じゃなくて、今の生活を維持するのに必要な最低金額」を出すこと。
たとえば──
| 項目 | 内容 | 金額(月) |
|---|---|---|
| 家賃 | 地方で実家暮らしなら 0円〜1万円(光熱費含) | 0〜10,000円 |
| 食費 | 自炊中心なら月1万5千円前後 | 15,000円 |
| 通信費 | 格安SIMで1,500円/Wi-Fi入れても | 3,000円 |
| 雑費 | 医療、日用品、たまの外食など | 5,000円 |
| 合計 | 最低限で生きるコスト | 23,000〜35,000円 |
これが都市部なら、簡単に2倍3倍になる。
つまり、「今の暮らし」がどこかで成り立っているかどうかが超重要ってわけ。
親の家に住んでるなら「逃げ道レベルEASY」
もしあなたが「親元にいられる」「家賃がない」状態なら、正直チャンス。
最低限の生活コストさえあれば、働く頻度をコントロールできる状態に近い。
たとえば:
- 週2日だけUber Eatsや配達のバイト
- 在宅でアンケートや文字起こしで月1〜2万円
- スマホ1台でポイ活&フリマ出品
これだけでも、「働いてはいるけど、ほぼ休んでる」ってくらいの生活ができるかもしれない。
都会で一人暮らしなら? コストを見直すか、居場所を変えるか
東京や大阪に住んでいて、「働きたくない」と思っているなら、まず“固定費”の見直しが必要だ。
- 家賃:月7〜9万円 → シェアハウスやマンスリーで半分に
- 食費:外食やUber常習 → スーパー×自炊×冷凍保存に
- 通信:大手キャリア → 格安SIM+フリーWi-Fi活用
それでも難しいなら、いっそ“逃げ場所”を変えるという手もある。
最近は、「移住 × 最低限労働 × 自然と共に」みたいな選択肢もリアルにあるからね。
「働かないで生きる」ではなく、「無理しないでつなぐ」方法
ボクがたどり着いたのは、これ。
✅ 働かない → ✕
✅ 無理しない → ◎
- 毎日フルタイム? ムリムリ
- 嫌な上司に頭下げる? 無理
- 興味のあることを、自分のペースで? それならちょっとだけ
具体的にはこんな方法がある:
| 方法 | 現実性 | コメント |
|---|---|---|
| クラウドワークスで記事執筆 | ★★★ | スキル不要なタスクも多い |
| ココナラで趣味販売 | ★★ | アイデア次第で小収入に |
| ショットワークで1日だけ働く | ★★★ | 体力不要の軽作業もあり |
| 生活保護や支援制度 | ★★ | 条件はあるが“休む”ことも選択肢 |
「働きたくない」=「逃げ」ではない。むしろ“戦略”
昔は、逃げたら負けだった。
でもボクは、いまの世の中は「逃げ方のセンス」が必要だと思ってる。
- 心を壊す前に、逃げる
- 合わない環境から、離れる
- 少し休んで、また次を考える
これ、負けじゃない。
むしろ、「ちゃんと自分を守ってる」ってことじゃないかな。
終わりに:生きるペースは、自分で決めていい
働きたくないなら、働かなくてもいい。
ただし、それを成立させるには、“自分のコストと環境”を見つめることが必要になる。
働くのが苦しいのは、あなたのせいじゃない。
社会の仕組みや時代の変化、何より「みんな違う」ってだけの話。
このブログ「にげログ」は、そんなふうに**“逃げながらでも、自分を壊さずに生きる方法”**を、ニゲルと一緒に探していく場所。
今日はここまで。
今度「実際に週1〜2だけ働いて生きている人の話」も紹介するね。